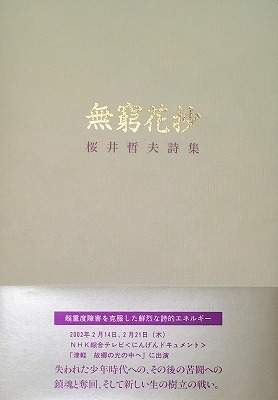
1994年5月、土曜美術出版販売から刊行された桜井哲夫の第3詩集。装幀は居島春生。
視覚障害者である私には文字がない。文字を持たない私の詩は、すべて代筆者によって文字となり詩となるのです。
詩作を始めて十年、第一詩集『津軽の子守唄』、第二詩集『ぎんよう』、この度はまた第三詩集『無窮花抄(むくげしよう。)』も、すべて盲人会職員の代筆によって生まれたものである。加えて、声帯を冒されている私の言葉を文字にしてくれた盲人会職員に只々感謝のほかない。
第三詩集の発刊を考えてくれたのは、昨年八月二十八日御逝去なされた故村松武司先生でした。先生は病院のベッドにありながらも、「君の第三詩集は必ず私が発刊するから」と、人を通して伝えてくださったのですが、遂にその志を果すことなく逝去なされたのでした。悲しみの極みです。
この度、村松先生の後任として森田進先生を、栗生詩話会の選者にお迎えしました。早速森田先生に跋文の労を頂き、第三詩集の発刊を見ることになりましたことは、喜びに耐えないところです。森田先生、本当に有難うございました。この詩集発刊によって村松先生の霊が慰められますように、と祈っております。
この度もまた、西毛文学の斎田先生には出版印刷の労を頂き、更に解説を加えて頂きました。深く感謝申し上げます。
(「あとがき」より)
世紀末が言われるが、二十世紀は思想の対立と数度の大戦と、激動といっていい時代の現実を私達は生きてきた。そして今思想の崩壊がいわれ、指標なき混沌の中で生きている。どのような新しいヒューマニズムを探求するかが、私達の詩的課題といえよう。
桜井哲夫を語るとき、そうした歴史の視点を当てずにはいられない。日本の近代から現代への激動期に、最も現実的にその時代苦を背負った一群の人達に、ハンセン病者があり、桜井哲夫もその一人であるからである。彼が所属している国立療養所草津楽泉園、栗生詩話会の人々と私が交流を持ってから、まだ十年程しかたっていない。其処には、外側の社会からは想像の及びもしない、ハンセン病者達の歴史的現実があったのである。苛酷な闘病生活と非人間的な差別と隔離の、運命的な暗黒な生活があったのである。そして一九四五年の敗戦を境に、平和憲法下のまがりなりのヒューマニズムの回復とともに、遅ればせながら戦後社会の福祉行政の陽の目をみるようになるのである。今、ハンセン病は治癒可能で、全国に散在する十余ヶ所の国立療養所は全くの自由開放区になっている。
国立療養所草津楽泉園が開所したのは昭和七年で、それ以前にハンセン病に対する国の施策は無策放置で過されてきた。桜井哲夫が同園に入所したのは昭和十一年で十七歳であった。家郷肉親との別離、入所しても治療薬もなく、病勢は進行にまかせるといった悲惨な運命であった。故郷津軽地方で過した少年時の身心ともに豊かな生命体は、全身的に蝕まれて、全身の重度障害、失明まで強いられてきた。このことは草津楽泉園に共に入所していた千数百人に及ぶ人達も、全く同じ運命共同体的な現実であった。非人間的受難の極限状況の中で、どう一個の人間として生命を維持するか、信仰、人間凝視、そして言葉による表現、桜井哲夫をふくめて、療養所入所者の文学表現の原点は、この時代の歴史の現実に通底していることを、先ず強調したいのである。
ハンセン病者の文学作品はすでに戦前期から注目されてきていた。詩部門では早くも大江満雄氏が作品集の発刊や、直接栗生詩話会への詩作アドバイスの温かい手を差しのべていた。戦後期に至っても村松武司氏が、昨年病没されるまで長期間、作品選評に当っており、更にその後任として新鋭の森田進氏が継がれることになった。
桜井哲夫が栗生詩話会で詩作を始めたのは一九八三年で詩歴は決して長くはない。然し詩的エネルギーは旺盛で、一九八八年第一詩集『津軽の子守唄』を、一九九一年に第二詩集『ぎんよう』を出版している。第一詩集は暗い闘病生活の中でのヒューマニズムと、故郷津軽への望郷の念が主旋律で、すでに失明状態のなかでの鮮明な詩的イメージの表現力で、その才能をうかがわせていた。
第二詩集に至っては、閉ざされた療養所の闘病生活の枠にとどまらないで、その詩的視野を外側社会にまで拡げて思想的時代感覚まで作品化を試みる詩的成長をみせていた。同時に群馬県内から出ている同人詩誌、西毛文学にも同人加入して、超重度障害を克服しての詩的エネルギーで作品活動を続けてきて、今回第三詩集『無窮花抄』を編むに至ったのである。
著者の「あとがき」にもあるように、この第三詩集は栗生詩話会の長期にわたる選評者として、親密な間柄にあった村松武司氏が出版にかかわる労をとってくださる筈であった。同氏の他界のためそれが果せなくなり、私が第二詩集に引き続いて原稿段階から詩集作りを手伝うことになった。正直なところ『津軽の子守唄』『ぎんよう』の二冊は、療養所関係者と、群馬県内の関係者に読者範囲は止まっていたといえる。桜井哲夫の持つ人間的環境的条件と、重度障害者のハンディキャップを克服しての鮮烈な詩的エネルギーは、その豊かなイメージ表現とともに一地方の出版物に止めるべきではないとの思いがあった。 たまたま今回、栗生詩話会の選評者の任につかれた森田進氏へも、著者からこの第三詩集出版への協力方を依頼されているので、私からも改めてアドバイスをお願いして、このような出版の形態をとることが出来たのである。
人間の命の姿がどのように表現されているかが文学の評価の基準である。この詩集が日本の詩界の内外に、更に一般社会においても一冊でも多く読まれることを、編者として願うばかりである。
(「極限状況の詩的エネルギー/斎田朋雄」より)
目次
第一章
- 年輪
- 文字のない木
- 旗揚げ
- 雪の降る夜には
- 一人ごっこ
- 草津じょんがら
- 冬の手紙
- 風の造形―一九九二・八・二五―竜飛岬にて
- 酔蝶花
- エアメールの中の花嫁
- 薬包紙
- 冬の蛾
- 炎―鎌原観音堂にて―
- チョゴリの歌
- 無窮花の花は何時開く―故村松武司先生におくる―
第二章
- 雪ながれ
- 宿り木
- 雪壁
- 雪女
- 花道
- 山葵がきいています
- 夜の庭
- 晩秋
- 目かくしだあれ
- 葉脈
- 落書
- かすみ草
- 榛名グラス
- 消印のない手紙
- 春雷
跋 森田進
解説 極限状況の詩的エネルギー 斎田朋雄
あとがき